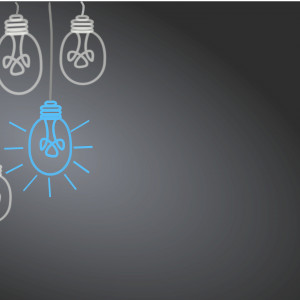社内SEを採用するメリットとデメリットとは?
SEを外注するのではなく、社内で採用した場合どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
また採用する時の注意点などを説明していきます。
目次
SEの必要性とは
SEの需要は経済産業の情報をみても高まっていることがわかります。
しかし需要に対して、人材不足であるのが現状です。
経済産業省が平成28年に公表した調査(※2)によると、2019年のIT人材は供給数が約92万人に対し不足数は約27万人となっています。
システム開発などのITニーズは今後も拡大する見込みですが、少子化などによる労働者人口の減少に伴い、今後ますます人材不足が深刻化すると予測されます。
また、経済産業省の別の調査(※3)でも、生産性の上昇率とIT需要の伸びを考慮した6つのシナリオのうち、5つのシナリオにおいて2030年にIT人材が大幅に不足することが推計されています。
※2 参考:経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果(平成28年6月10日)」
※3 参考:経済産業省委託事業「IT 人材需給に関する調査(平成31年3月)」
引用:レバテックキャリア
社内SEを採用するメリット
まず社内SEを採用するメリットを説明していきます。
- 企業にあったシステムを開発できる
- いつでも保守作業できる
- 企業の情報が漏れることがない
企業にあったシステムを開発できる
システムを外注する場合、企業の業務内容や方針などにあったシステムを開発できるとはかぎりません。
また合わないシステムを導入してしまうと、かえって時間がかかってしまいます。
しかし自社で社内SEを採用するのであれば、それぞれの企業の業務内容などにあったシステムの開発が可能になります。
いつでも保守作業できる
システムの運用には、保守作業がつきものです。
しかし外注であれば、すぐに対応してくれるとはかぎりません。
しかし社内SEを採用することにより、必要な時に即座に保守作業をすることができるのです。
また保守作業しやすいように、開発時から考えることもできます。
企業の情報が漏れることがない
外注したりSESなどに依頼する場合、企業の情報が漏れる可能性はゼロではありません。
また情報漏洩まで行かなくても、ノウハウなどが漏れる可能性もあります。
しかし社内の人間であれば、この点安心度が高いです。
社内SEを採用するデメリット
ここまで社内SEを採用するメリットを説明してきましたが、以下のようなデメリットもあります。
- コストがかかる
- 能力のある人を採用できるとは限らない
- 人材の教育が大変
- 管理者もSEの知識が必要
コストがかかる
社内SEを採用するためには、求人広告費に記載したり面接をしたり、また研修などをするなどコストがかかります。
また定期的に研修をする必要があり、採用してからもコストを考える必要があります。
能力のある人を採用できるとは限らない
広告費用をかけて面接までしても、能力のある人を採用できるとはかぎりません。
さらに現在は少子化で、IT人材が不足している点もさらに厳しい状況となっています。
つまり広告費用や面接費用などをだしただけで、納得のいく人材を採用できないケースもあるのです。
人材の教育が大変
システムエンジニアは定期的に新しい情報や技術が必要になってきます。
そのため定期的に採用をしたあとも、人材の教育を続ける必要があります。
そのためには教育できず人材も必要になります。
管理者もSEの知識が必要
社内SEを採用する場合、管理者もSEの知識が必要になります。
知識がない人が管理はできず、また何かあった場合責任を取る必要もあるのです。
完全に業務委託をしたり、外注する場合は責任者は外注先にもあるので、この点で大きな違いがあります。
SEを外注するメリット
社内SEを採用しない場合は、外注をする場合になります。
社内SEを採用する場合と比較して、外注する場合のメリットは以下の点になります。
- 専門知識は必要ない
- 手間や時間をかける必要がない
- トラブルがあっても対応してくれる
- 余分なコストは必要ない
- 必ずシステムは運用できる
専門知識は必要ない
業務は完全に依頼をすることができるので、専門知識は必要ありません。
途中で研修をする必要もなく、すべてを任せることができます。
しかし進捗状況などを把握するために、最低限の知識は持っておくことが必要です。
外注するにしても、ベンダーさんと一緒にシステムを作り上げていくイメージは大切です。
手間や時間をかける必要がない
システムを開発、運営、保守作業をする手間や時間はかける必要がありません。
またSEを採用、教育こともないので、手間や時間を省くことができます。
しかしベンダー任せにするのではなく、システムを作る目的などは把握しておくようにすることが重要です。
トラブルがあっても対応してくれる
自社でシステムを構築する場合は、トラブルがあった場合自社で対応する必要があります。
しかし外注する場合は、外注先が対応してくれます。
保守作業までしっかりとしてくれる外注を選ぶことが重要です。
余分なコストは必要ない
SEを採用する場合、広告費や面接をする費用が必要になりさらに採用できるとは限りません。
またうまく育ってくれるとも限りません。
外注をする場合このようなコストをかける必要はありません。
必ずシステムは運用できる
社内SEを導入する場合、思っているレベルのSEを採用できるとはかぎらず、場合によってはシステムを構築できるとはかぎりません。
しかし外注をする場合、しっかりと業者を選ぶと必ずシステムを運用できます。
つまり外注を依頼すると、ある程度の目標がたちやすいということです。
SEを外注するデメリット
ここまで社内SEを外注するメリットを説明してきましたが、デメリットもあります。
- 業務にあったシステムができるかわからない
- コストが高くなる可能性がある
- 従業員が使いこなせるかわからない
業務にあったシステムができるかわからない
業務の内容にあったシステムができるとは限りません。
社内SEであれば、企業の業務内容や方針などにあったシステムを構築することができます。
導入前に十分打ち合わせをしていないと、あとから思ったようなシステムができないなどトラブルになる可能性もあります。
コストが高くなる可能性がある
企業の規模によって、外注するとコストが高くなるケースもあります。
前もって概算をしておくことが重要です。
また導入後の効果測定も大切です。
従業員が使いこなせるかわからない
いくらいいシステムであっても、従業員が使いこなせないと意味がありません。
そのため従業員が使いこなせるような、わかりやすいシステムを作ることが重要です。
SESを採用するメリット
システムを導入する場合、SESを採用する方法もあります。
ここではSESを採用するメリットを説明していきます。
- 必要な労働力だけ採用できる
- 社員を採用するよりもコストを抑えられる
必要な労働力だけ採用できる
例えばいきなりできたプロジェクトなどの場合、従業員を採用するには人を探すのが大変で、コストもかかってしまいます。
しかしSESであれば、必要な労働力だけ採用することができます。
社員を採用するよりもコストを抑えられる
SESであれば、募集広告をしたり教育費用もかかりません。
またプロジェクトが終了したあとの問題も、SESであれば心配ありません。
そのため社員を採用するよりもコストを抑えられることがあります。
SESを採用するデメリット
SESのメリットを説明してきましたが、デメリットも以下のようにあります。
- プロジェクトを終了するかわからない
- ノウハウが外に漏れることがある
プロジェクトを終了するかわからない
SESは業務請負と違い、労働時間で契約をします。
そのためプロジェクトが終了するとは限りません。
そのためSESにすべてを任せるということはありません。
社員SEを採用して、足りない分をSESに依頼するケースが多いです。
ノウハウが外に漏れることがある
社内のノウハウなどが外に漏れる可能性があります。
SESは契約が終わったら、競合会社と契約をする可能性もあるのです。
まとめ
システムエンジニアを採用する場合主に以下の3つのパターンがあります。
- 社内SE
- 外注(業務委託)
- SES
それぞれのメリット、デメリットをもう一度まとめます。
社内SEを採用するメリット
- 企業にあったシステムを開発できる
- いつでも保守作業できる
- 企業の情報が漏れることがない
社内SEを採用するデメリット
- コストがかかる
- 能力のある人を採用できるとは限らない
- 人材の教育が大変
- 管理者もSEの知識が必要
SEを外注するメリット
- 専門知識は必要ない
- 手間や時間をかける必要がない
- トラブルがあっても対応してくれる
- 余分なコストは必要ない
- 必ずシステムは運用できる
SEを外注するデメリット
- 業務にあったシステムができるかわからない
- コストが高くなる可能性がある
- 従業員が使いこなせるかわからない
SESを採用するメリット
- 必要な労働力だけ採用できる
- 社員を採用するよりもコストを抑えられる
SESを採用するデメリット
- プロジェクトを終了するかわからない
- ノウハウが外に漏れることがある
ここまでを比較しても、社内SEを採用するメリットは自社の業務にあったシステムを作ることができ、また情報が外に漏れないことがあげられるでしょう。
デメリットは採用活動や教育が大変なことがあげられます。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。