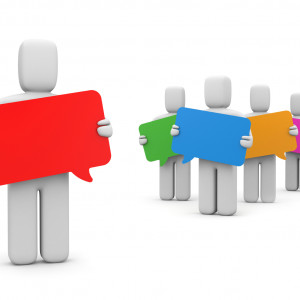企業のテレワーク推進を妨げる請求書に関する業務を改善する開発パートナー選びのポイント
2019年12月に新型コロナウイルス感染症が世界中へパンデミックを引き起こしました。
政府・都道府県知事は企業・団体に在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務を要請しました。
一方では、同年4月に「働き方改革法」が施行され、働き方が多様化したことで、従来の事業所に出勤して業務をする必要が減少してきました。
しかし、日本国の商習慣でお客先様や取引先企業・団体に紙媒体の請求書を発送・郵送して代金の回収・支払いをしています。
そのため、在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務担当であっても「請求書」発行のために事業所に出勤しています。
2021年の年初に大手ベンダー企業が「請求書」発行にかかわる業務で事業所に出勤している企業・団体(経理・会計・財務部門を除いています。)に向けて、紙媒体「請求書」発行をするために出勤しているか否かのアンケート調査を実施しました。
結果は、回答企業全体の82.5%と高い数値になっています。
経理・会計・財務部門以外で「請求書」発行のために出勤する現実が明らかになりました。
企業・団体は、従業員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者・陽性者・罹患者にならないように防衛するとともに、多様な働き方改革を推進することが求められています。
そこで、在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務をしながら「請求書」発行に関する業務の課題の紹介と、改善すべきポイントを紹介していきます。
目次
1.企業のテレワーク推進を妨げる請求書とは何か?
在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務が広まりをみせています。
しかし、この働き方を妨げているものが、紙媒体の「請求書」なのです。
2021年にビジネスマン1,000人に「請求書」を取り扱う部門は経理・会計・財務部門との回答が8割を大きく超えました。
実際には経理・会計・財務部門以外の営業部門・販売部門・購買部門・仕入部門などでは、従業員の5人に4人以上の割合で、紙媒体の「請求書」を取り扱う業務で出勤しています。
紙媒体の「請求書」ために出勤している理由は、紙媒体の「請求書」発行ではなく、「請求書」の受け取りという結果になりました。
企業・団体は早急に対策をすすめることが急務になっているようです。
企業・団体の基幹業務は、在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務で対応できるようにインフラ環境の改新・改善、基幹業務システムをクラウドコンピューティング・サービスへ移管するよう更新されてきました。
しかし、社外のお客先様・取引先様から送付される「請求書」は紙媒体で郵送されてきます。
紙媒体の「請求書」を受領する・支払い申請をするために事業所に出勤することは、大きなストレスになっているようです。
2.テレワークで変化する請求書の処理フロー
テレワークで変化する「請求書」の処理フローを紹介します。
前章で紹介しましたが、在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務が広まりをみせています。
そのなかで、お客先様・お取引先様から紙媒体の「請求書」の取り扱い方法を紹介します。
在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務中に紙媒体の「請求書」は事業所へ郵送されます。
従来は事業所において紙媒体の「請求書」を開封して、内容の確認・照合をして支払い申請を作成して支払い部門に送ります。
しかし、在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務の処理フローに紙媒体の「請求書」を取り扱う工程が明確にされていないケースが多く、処理フローを一時的に「出勤して対応」する作業に変更して対応したとの声が多くありました。
また、紙媒体の「請求書」を原本ではなく、データ化して処理フローにのせるケース、お客先様・お取引先様に紙媒体の「請求書」をデータ化してeメールで提出するよう改善したケース、紙媒体の「請求書」を基に作成する支払い申請書の押印を電子化して対応したケースなどがあげられます。
在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務に移管しても、郵送される紙媒体の「請求書」の取り扱いは、処理フローに組み込まれないため、従業員の負荷がかかります。
さらに日本国の商習慣である押印の手続きを見直す必要があります。
2022年4月に施行された「改正電帳法」では押印をタイムスタンプに置き換えることができますが、社内の処理フロー・業務フローを見直す必要があるようです。
3.テレワークで請求書処理をするために必要なこと
在宅勤務・テレワーク勤務・リモートワーク勤務で「請求書」処理を滞りなくするために必要なことを紹介します。
第1に紙媒体の「請求書」の授受を郵送から、PDFなどのデジタルデータに変更してもらい、eメールで送信してもらうよう改善することです。
紙媒体の「請求書」は、お客先様・お取引様との代金授受に関する重要なエビデンスです。
そのため、社判が押印された紙媒体の「請求書」を一定期間保存する必要があります。
2022年4月の「改正電帳法」ではタイムスタンプに置き換える手続きが簡略化されました。
また、紙媒体の「請求書」保存から、デジタルデータで保存することが容認されました。
(但し、当該のエビデンスがすぐに検索・表示される条件をクリアすることが求められます。)紙媒体の「請求書」を郵送で受領することは、お客先様・お取引先様の担当部門が紙媒体の「請求書」を発行して、押印・発送をしています。
お客先様・お取引先様と協議して紙媒体の「請求書」をデジタルデータ化に移行することで、双方にメリットがあるはずです。
紙媒体の「請求書」をデジタルデータ化することで、発行する側・受領する側の従業員が事業所に出勤して対応する必要が軽減されます。
しかし、IT化導入が遅れていて、どうしても紙媒体による取り扱いがあるときは、出勤する従業員を事前に調整し、最小工数で対応できるようにしましょう。
第2に紙媒体の「請求書」をデジタルデータで発行できるようにシステムを改新することです。
紙媒体の「請求書」をデジタルデータ化することは、該当業務を改新する必要があります。
改新するために費用がかかるので、即時に対応することが難しい企業・団体があることでしょう。
そのための準備期間と改造費用の確保が必要です。
そのため、デジタルデータで請求書を発行・送付できる請求書発行システムが注視されています。
2022年4月施行の「改正電帳法」、政府が掲げているペーパーレス化の推進によって、請求書のデジタルデータ化の動きは加速していきます。
請求書をデジタルデータ化できないときは、請求書を出力するとき紙媒体ではなく、PDFファイルに出力する機能がありますので、活用してみましょう。
それでもデジタルデータ化できないときは、スキャナーで読み込んでデジタルデータ化する手法も検討しましょう。
第3に紙媒体の「請求書」の社内回覧・承認・処理の業務フローを電子化することです。
紙媒体の「請求書」からデジタルデータ化された「請求書」に移管することで、企業・団体の社内フローに組み入れることができます。
但し、社内の業務フロー・ルールを整備する必要があります。
いままで紙媒体の「請求書」をデジタルデータ化できる仕分けをして、デジタルデータ化できるものは、業務フローに取り入れます。
さらに、業務フローマニュアルを改修する必要があります。
より効率的な業務フローを推進できる体制を整えておくことが必要です。
4.企業のテレワーク推進を妨げる請求書に関する業務を改善する開発パートナー選びのポイント
デジタルデータ化した「請求書」を基幹システムに反映すること・いままで紙媒体の「請求書」であったものをデジタルデータ化して業務フローに組み入れるときの対応は、企業・団体が導入している基幹システムの開発パートナーに相談してみることをお勧めします。
また、企業・団体が導入している基幹システムの経理・財務・会計サブシステムには、電帳法に対応しているケースがあると思います。
さらに現行のシステムに「改正電帳法」機能が組み込まれているケースがあります。
現行の基幹システムを導入した開発パートナーの営業担当や開発プロジェクト・マネジャーに確認してみましょう。
「請求書」のデジタルデータ化の検討は、企業・団体が導入している基幹システムの開発パートナーに事前相談してみることをお勧めします。
大手電機メーカー、ITベンダー企業、ITベンチャー企業は基幹システムをする部門以外に「ペーパーレス化/改正電帳法」をサポートする担当エンジニアをスタンバイさせています。
現行の基幹システムを導入した開発パートナーの営業担当やプロジェクト・マネジャーに相談してみましょう。
まとめ
在宅勤務化・テレワーク・リモートワークに限らず、今後経理・会計業務においてペーパーレス化が推進されていきます。
従来の紙媒体による「請求書」をお客先様・お取引先様と協議しながら、デジタルデータ化して業務効率を改善することをすすめましょう。
紙媒体の「請求書」の取り扱いをデジタルデータ化することで、双方にメリットがあるはずです。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。