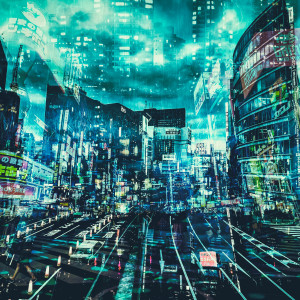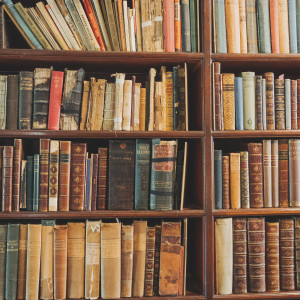システム導入したときの資産の計上の仕方とは?
システムを導入した金額は、確定申告のときにどのように申告すればいいのでしょうか。
システム導入は固定資産税として計上する場合と、経費として計上する場合と条件がそれぞれ異なります。
目次
システム(ソフトウエア)の取得価額と耐用年数
まずシステム(ソフトウエア)の計上方法ですが、取得価額を耐用年数によって変わってきます。
取得価額と耐用年数は国税庁によって以下のように記載されています。
取得価額
購入した場合だけでなく、自社で制作した場合でも対象となります。また取得価額に算入しない金額もあるので確認が必要です。
(1) 取得の形態による取得価額の計算方法
イ 購入した場合
購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用
この場合、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。
ロ 自社で製作した場合
製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用
(2) 取得価額に算入しないことができる費用
次のような費用は、取得価額に算入しないことができます。
イ 製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用
ロ 研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
ハ 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
引用:国税庁
耐用年数
耐用年数は販売目的もしくは研究開発であれば5年間、残りはすべて3年間となります。
(1) 「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
(2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年
引用:国税庁
システムは固定資産に計上する
システムは損益計算ではなく、貸借対照表に構成される科目となります。
売り上げではなく、資産や負債、純資産で構成されているのが貸借対照表なのです。
会社の財産として、将来的に会社にとって利益をもたらす価値があるといった考え方になるのです。
具体的には固定資産として計上するためには、以下の条件がそろっていることが必要です。
固定資産に計上できる条件
- システムでもうけを出す目的ではない
- 1年以上利用する予定
- 10万円以上のもの
システムでもうけを出す目的ではない
システムを固定資産に計上するためには、システムを儲けににする目的で使わないことが必要になります。
もし儲けに使うようであれば経費での計上となります。
1年以上利用する予定
将来的に利益をもたらすものとった目的になるので、1年以上利用する予定であることが条件となります。
そのため短期間で利用しようとしているシステムに関しては、対象外となる可能性があります。
10万円以上のもの
システムの費用が10万円以上のものが対象になります。
そのため小規模のクラウド型システムなどは対象外になる可能性もあります。
10万円未満の場合は、経費として計上することになります。
減価償却の償却年数
減価償却の償却年数の年数ですが、以下のように自社利用目的と販売目的によって年数が異なります。
自社利用目的ソフトウェア:償却年数5年
販売目的ソフトウェア:償却年数3年
ただ企業対象の特別な条件があり、固定資産の条件にあてはまっていても経理計上することもできます。
経費計上すると減価償却の必要はなくなります。
それではその特定を説明します。
この特例とは国税庁が定めている令第138条及び第139条関係の、少額の減価償却資産及び一括償却資産です。
令第138条又は第139条の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。
引用:国税庁
この法令にあてはめて考えると、以下のようになります。
通常の場合
| 10万円以下 | 10万円以上20万円未満 | 20万円未満30万円以上 | 30万円以上 |
| 消耗品費 | 一括償却資産 | システム | システム |
「少額の減価償却資産及び一括償却資産」適応
| 10万円以下 | 10万円以上20万円未満 | 20万円未満30万円以上 | 30万円以上 |
| 消耗品費 | 一括償却資産もしくは消耗品費 | システムもしくは消耗品費 | システム |
つまり少額の減価償却資産及び一括償却資産を適用した場合は、10万円以上30万円未満のシステムに関しては、消耗品費つまり経費として計上することもできます。
システム導入時の会計処理の仕方
システム導入時の会計処理の仕方は、実は複雑になっています。
それぞれの条件で説明していきます。
無形固定資産税に計上した場合
システムで20万円以上の場合は、無形固定資産」に計上して減価償却することになります。
工事代金などのオプションもすべて計算に入れて問題ありません。
減価償却は5年でするものとし、システム導入代金の総合計が120万円として説明していきます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| ソフトウエア | 1,200,000 | 預金 | 1,200,000 |
毎月の仕分け(定額法を使った場合)
120万円を5年なので5で割り、さらに12か月分でわります。
120万÷5÷12=2万
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| ソフトウエア | 20,000 | 減価償却累計額 | 20,000 |
システムを資産計上するときのポイントとは
システムは条件によって固定資産として資産計上するのですが、以下の点に注意をするようにしてください。
IT導入補助金を使う場合
条件にあっている必要がありますが、システムを導入する場合IT導入補助金の対象になる場合があります。
もし対象になった場合は圧縮記帳が可能になります。
圧縮記帳とは補助金などある一定の条件で固定資産を取得した場合は課税の繰り延べをすることをいいます。
つまり本来は課税所得となるものを将来に伸ばすことができる制度になります。
わかりやすく説明すると圧縮記帳をすることにより、固定資産(システム導入)の取得価格を減額し、減価償却費も少なくすることができます。
注意点が一点あり、資産管理面においてIT導入補助金の対象にならないものと区別して管理をすることが必要になります。
単純に手間ということだけを考えると、一つ増えることになるのです。
クラウド型のシステムを導入した場合
システムの種類として、オンプレミスとパッケージ、そしてクラウド型があります。
クラウド型を選んだ場合は、初期費用がほとんどかからず、毎月の必要がかかります。
クラウド型を1年上使う予定で、初期設定費用やカスタマイズ費用など、導入時に支払った金額が条件として設定している金額を超えると無形固定資産に計上になります。
また最初から契約期間が決まっている場合は、その契約期間が償却期間となります。
自社で開発した場合でも収益性があるかどうかで計上が変わる
自社で開発したシステムであっても、収益性があるかどうかで計上方法が異なります。
収益性が確実と判断されれば、資産とみなされます。
また収益性がない、もしくは確実ではないと判断されたら資産計上をする必要はありません(資産計上は可能です)。
また自社で開発をした場合は、開発をした従業員の人件費も経費として扱うことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
システム導入をした場合の計上方法ですが、システムの目的や取得価額などによって計上が異なります。
また「少額の減価償却資産及び一括償却資産」により通常は無形固定資産として計上するのですが、経費として計上できる場合もあります。
自社で開発した場合でも計上が必要になるので注意をしてください。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。