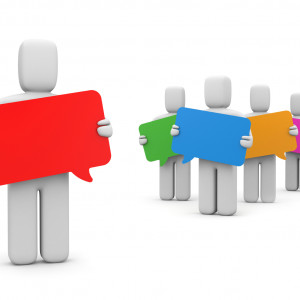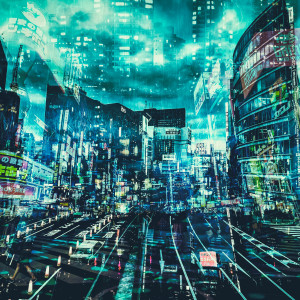ハイブリッドにシフトした働き方を継続推進する開発パートナー選びのポイント
2020年年初から未知の新型コロナウイルス感染症が拡大し始めて、いまだに収束する兆しがありません。
2020年3月に日本政府は「緊急事態宣言」を発出して、多くの企業・団体にリモートワーク・テレワークの協力要請をしました。
企業・団体は急遽リモートワーク・テレワークに切り替えをしました。
2021年秋まで、「緊急事態宣言」の解除・発出、「まん延防止等重点措置」の解除・発出が繰り返す状況に至っています。
企業・団体はオフィス勤務・リモート勤務を使い分けるハイブリッド勤務を導入するケースが増えています。
ハイブリッド勤務を導入することで、事務所賃借料等の固定費を見直す契機になる・従業員のワークライフバランスが改善される等のメリットがあります。
企業・団体は、ITインフラ環境の整備・改新をするなどの課題を多く抱えることになりました。
今後ハイブリッド勤務を継続する企業・団体は「どの点に」「どのように」対応すれば良いのか開発パートナーとともに再検討することなります。
これからハイブリッド勤務のすすめ方を紹介していきます。
目次
1.ハイブリッドにシフトした働き方とは何か?
「ハイブリッド勤務」とは従来通り「事業所で勤務」と「自宅でリモートワー/テレワーク」のメリット合わせた働き方を称します。
新型コロナウイルス感染症拡大により日本政府は企業・団体に事業所勤務者の7割を「自宅でのリモートワーク/テレワーク」等の在宅勤務をするよう要請しました。
そのため2020年春頃から、急速にリモートワーク・テレワークが拡大しています。
企業・団体によっては賃借しているオフィスを縮小して、従業員にリモートワーク・テレワークを推奨しているケースがあります。
先進的な企業・団体は、リモートワーク・テレワークが効果的に機能しているため「オフィス不要論」「事務所不要論」が囁かれています。
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しができないため、今後もリモートワーク・テレワーク傾向は続くと見られています。
そのなかで、増殖している働き方が、「ハイブリッド勤務」というワークスタイルです。
業務の多くをリモートワーク・テレワークによって担います。
週に1日~2日を事業所・事務所・オフィスで就業するスタイルです。
「オフィス勤務」と「自宅でのリモートワーク/テレワーク」のメリットを合わせた働き方です。
リモートワーク・テレワークでの勤務をする日々は、コミュニケーションを円滑にするためにオンライン会議・オンライン例会等のミーティングを高頻度で実施します。
新型コロナウイルス感染症拡大前に勤務状態である「週5日出勤」の既成概念にとらわれず、柔軟性をもった働き方に移行しています。
新型コロナウイルス感染症が収束しても「ハイブリッド勤務」を継続する企業・団体が多いようです。
2.ハイブリッド勤務はなぜ、企業の生産性を高めるのか
「ハイブリッド勤務」を導入すると、企業・団体の生産性を高めるといわれています。
これからその理由を紹介していきます。
第1に固定費削減に伴う余剰予算を生産性向上につながる資源に投下できることです。
「ハイブリッド勤務」を導入している企業・団体のなかには、従業員の3〜4割程度の固定机・席を用意して、残りをフリー机・席制に切り替えるケースがあります。
事務所の坪数を削減することで、事務所賃料・水道光熱費等の固定費を軽減できます。
固定費を軽減した資金をIT機器の更新・事務機器の更新に充てることができ、生産性向上につながります。
第2に従業員のワークライフバランスを見直して、定着につながります。
「ハイブリッド勤務」を導入している企業・団体のなかでは「都心から郊外へ引越しをした」「郊外への転居を検討している」という従業員が出始めています。
企業・団体の近くに居住する必要がなくなり、子育てに最適な環境を選択できるのです。
また、都心の狭い住居から郊外の広い住居でリモートワーク・テレワーク室を確保することもできます。
「ハイブリッド勤務」は従業員のワークライフバランスを考えるきっかけになっています。
さらに従業員のワークライフバランスを考慮することで、定着率を向上させます。
第3に多用な働き方で柔軟に業務をこなす能力が身に付くことです。
リモートワーク・テレワークへの移行は机上でパソコンや端末を使用した業種の方々が対象になります。
ただし、パソコンや端末を使用した業種であっても、接客を伴う職種はリモートワーク・テレワークへの移行はできません。
たとえば、金融機関業のケースでは、端末を使用しますが接客を伴うプロフィット部門は移行できません。
しかし、管理部門などのスタッフ系の部門は移行できます。
人事異動等でプロフィット部門・管理部門への配置転換があれば、それぞれリモートワーク・テレワークへの移行が可能になり、柔軟な働き方に実現ができます。
さらに、流行のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進している企業・団体は円滑にリモートワーク・テレワークへの移行ができます。
しかし、接客販売業界・医療福祉業界は、対人対応が前提の業務はリモートワーク・テレワークに向いていません。
また、製造業のように工場内で機械を扱う業務も、リモートワーク・テレワークに不向きなようです。
上記の業界でも最新IT機器によってリモートワーク・テレワークへの移行できる機会がくるでしょう。
第4にコミュニケーションスキルが向上することです。
毎日事業所へ出勤することがなくなれば、従業員間の接点がなくなります。
そのため、オンライン会議・オンライン例会などパソコン画面・端末画面を介したコミュニケーション維持を活発に実施する必要があります。
オンラインによるコミュニケーション維持が難しいことです。
そのため、画面を介した意思疎通の仕方を上手くするスキルが養われます。
リモートワーク・テレワークへの移行により「コミュニケーション不足を補うために、意思を伝えるスキルが向上した」という結果が多くなっているようです。
3.ハイブリッド勤務を実現するために必要なこと
「ハイブリッド勤務」を実現するために必要な諸項目を紹介します。
第1にITインフラ環境の整備です。
「ハイブリッド勤務」を実現するためにパソコン・タブレット端末・通信インフラを整備して、リモートワーク・テレワークへ移行する従業員へ機器を貸与する必要があります。
「ハイブリッド勤務」を導入するためには、ITインフラ環境を確実に整備することが必要です。
従業員に平等にリモートワーク・テレワークへ環境を貸与するよう、十分準備・支給することが重要です。
第2に情報漏洩リスクの対処を施す必要があります。
セキュリティー問題は「情報漏洩防止の仕組みを導入すること」「リモートワーク・テレワークの就業規則・社内規定を整備して従業員に徹底すること」「従業員別に情報へのアクセス権を設定すること」等の対策を整備する必要があります。
第3に従業員の勤怠状況を管理するための仕組みを導入することです。
リモートワーク・テレワークは、従業員の勤務時間を管理することが難しいため、自己申告制か支給した機器の稼働状況に応じた勤怠管理する等の対策が必要になります。
現在は、リモートワーク・テレワークに対応した勤怠管理アプリケーションが販売されています。
4.ハイブリッドにシフトした働き方は今後どうなるか?
ハイブリッド勤務にシフトした働き方は今後どうなるでしょうか?新型コロナウイルス感染症が収束した後も、リモートワーク・テレワークは継続して運用されると予想されます。
前章で紹介しましたが、企業・団体の事業所坪数の削減・固定机と席の削減をして固定経費を削減しています。
また、従業員の居住地を郊外に転居するなどのライフワークバランスを改革しました。
そのため、新型コロナウイルス感染症が拡大前の就業形態(朝9時~夕方17時は事業所で勤務する)に戻すことは難しいようです。
企業・団体は適宜にリモートワーク・テレワークを取り入れ、「ハイブリッド勤務」を継続すると予想されます。
リモートワーク・テレワークへの移行時点は不具合がある・プロジェクトチームの統一感がないことが、工夫によって改善され最適な環境に遷移します。
「混雑している通勤電車で通勤する」「移動時間をかけて訪問・出張する」ことを思い浮かべると「ハイブリッド勤務」を継続する方向にすすむと予想されます。
5.ハイブリッドにシフトした働き方を継続推進する開発パートナー選びのポイント
ハイブリッドにシフトした働き方を継続推進する開発パートナー選びは、現在使用しているリモートワーク・テレワークへ移行した際の開発パートナーを継続して選定しましょう。
リモートワーク・テレワークへ移行した従業員へ支給したパソコン・タブレット端末・通信インフラ機器は、開発パートナー企業を介して導入していることでしょう。
保守・運用面に観点から開発パートナー企業を継続することをお勧めします。
まとめ
「ハイブリッド勤務」導入でコミュニケーションの重要性は変わらないでしょう。
「ハイブリッド勤務」で不完全なオンライン会議に不便さを感じた方もいることでしょう。
しかし、「ハイブリッド勤務」が日常化することで、慣習化され不便さが改善されます。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。