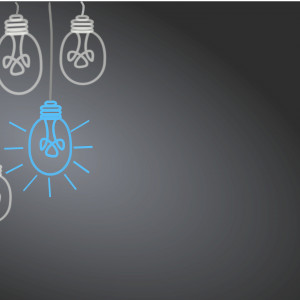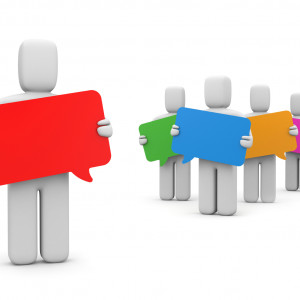中小企業経営者が知るべきシステム開発の基礎知識を営業する開発パートナー選びのポイント
近年、世界的に情報システム・情報技術(IT)への需要が高まっています。
なんと、世界時価総額ランキングのトップ10のうち8社がGoogle社・Apple社・メタ社・amazon社などの大手IT技術開発・供給企業なのです。
情報技術(IT)の用語で「システム開発」という用語がありますが、みなさんご存じでしょうか。
情報系にかかわりがない方々は、名前は知っているけど中身はわからない・イメージがわかない方々が多いようです。
特に中小企業・零細企業の経営者は、自社の設備投資に積極的なことに対して、情報システム投資は消極的といわれています。
このままでは事業継続が厳しいといわざるを得ません。
これから、情報技術(IT)初心者の方でもわかるように「システム開発」について紹介していきます。
また、「システム開発」を経営に活かす方法について紹介していきます。
「システム開発」の重要性をイメージしていただければ幸いです。
目次
1.システム開発とは何か?
「システム開発」は、「サービスや仕組みを作ること」です。
関連したIT用語で「プログラミング」があります。
「プログラミング」は、「システム開発」をすすめる工程のひとつです。
コンピューターが「サービス」「仕組み」を実行するための処理一つひとつに機械語に命令文を記述することをいいます。
「プログラミング」工程がないと「システム開発」ができません。
近年は「ローコード」「ノーコード」による「プログラミング」技法が開発されていますが、今回は触れずに一般的な「システム開発」を紹介していきます。
2.システム開発の目的
「システム開発」の目的を紹介します。
「システム開発」の目的は、コンピューター・システムを導入することで、コンピューターが作業をします。
企業・団体は、人件費の削減・業務の効率化を図ることができます。
しかし、コンピューターが不得意な分野もあります。
「システム開発」をしたことで、企業・団体が抱えている課題・問題が全て解決することはできません。
コンピューター・システムを導入して効果が発揮させる作業は、①計算作業、②単純な作業、③データの集計作業などです。
また、コンピューター・システムを導入しても効果が発揮できない作業は、①創造性がある作業、②判断・決断作業、③相手先の感情・気持ちを察することなどです。
3.システム開発の流れ
「システム開発」の流れを紹介します。
「システム開発」の流れは「ウォーターフォール」モデルの開発手法を基準にしています。
「ウォーターフォール」モデルは、上から順番に工程を一つずつ進めていく開発手法です。
第1は「要件定義」です。
要件定義は、「システム開発」の発注元と開発先が協議してシステムの機能範囲を決めます。
発注元と開発先間でシステムの機能・性能の認識に乖離がないように確認します。
要件定義の工程では開発元・開発先の認識を合わせることが非常に大切です。
第2は「設計」です。
「要件定義」工程が完了後に「設計」工程に遷移します。
「設計」は「外部設計」「内部設計」工程があります。
「外部設計」は、当該システムを操作するユーザーの観点で必要な機能を選定して、システムの全体像を決めていきます。
「内部設計」は、「外部設計」した設計書から単体レベルまでの詳細を設計します。
「内部設計」は、プログラム設計書に近いものです。
「外部設計」は「概要設計」「基本設計」と称する開発先があります。
「内部設計」は「詳細設計」と称する開発先があります。
この「設計」工程が「システム開発」全体の流れを決める重要な工程です。
第3は「製造」です。
「製造」とは、「内部設計」(または「詳細設計書」「プログラム設計書」)を基にして、コンピューター言語を使用してプログラミングをする工程です。
第4は「テスト」「試験」です。
「製造」したプログラムが「内部設計」(または「詳細設計書」「プログラム設計書」通りの動作確認をします。
プロジェクトによっては「テスト設計書」「テスト報告書」を作成して確認することがあります。
「テスト」工程は「単体テスト」「結合テスト」「総合テスト」「システムテスト」「総合運転テスト」などがあります。
「単体テスト」は上記で紹介しましたが、「製造」したプログラムが「内部設計」通りに動作することを確認します。
全ての「単体テスト」が完了すると「結合テスト」工程に遷移します。
「結合テスト」は「外部設計」通りに上の処理から下の処理まで、連続して動作することを確認します。
「結合テスト」が完了すること「総合テスト」に遷移します。
「総合テスト」は「外部設計」通りに時系列で動作することを確認します。
「システムテスト」「総合運転テスト」は、発注元の要件を満たしていることを確認します。
この工程で発注元も「テスト」工程に参画して、「要件定義」通りに動作することを確認します。
第5は「リリース」です。
「総合運転テスト」は何度も繰り返し行います。
「総合運転テスト」で問題がなければ、開発したシステムを発注元に納品します。
「リリース」は「カットオーバー」「S」と称する開発先があります。
第6は「保守」「運用」です。
開発したシステムを発注元に納品した段階で、撤収して完了することではありません。
「リリース」「納品」したシステムが継続して安定稼働するためにスタンバイします。
この工程を「保守」「運用」といいます。
システムの不具合・異常動作・異常終了のアフターフォローをしていきます。
4.スムーズなシステム開発を行うために意識すること
スムーズな「システム開発」を行うために意識することを紹介します。
第1に「要件定義」を固めることです。
「要件定義」を固めておかないと下位工程に歪みを生じることがあります。
その歪を補正するために、予定外の開発工数・開発コストが必要になります。
「要件定義」工程は基本方針を決める重要な工程です。
発注元・開発先間の乖離がない状況にすることが重要です。
第2に「システム開発」プロジェクトのコミュニケーションを円滑にすることです。
SE・プログラマーの1日の作業は端末に向かっています。
「システム開発」はプロジェクト全体で着地点を合わせることが求められます。
朝会・夕会などを開き進捗状況報告などを報告し合うことが必要です。
「システム開発」プロジェクト内での情報共有はもれなく全員が認識できる環境を整えましょう。
第3にプロジェクトメンバーのスキル・進捗の確認することです。
「システム開発」プロジェクトには、経験豊富な技術者ばかりではありません。
そのため、プロジェクト・マネージャーはプロジェクトメンバーのスキルを認識して、進捗管理をする必要があります。
5.システム開発を経営に活かす方法
「システム開発」を経営に活かす方法を紹介します。
第1に導入するシステムによって、今までの作業を効率化します。
「システム開発」の成果物によって、従来の作業がコンピューター化されます。
コンピューター化することで作業が効率化される範囲を明確することで、経費削減がはっきりとしていきます。
第2に「システム開発」の考え方を経営に活かすことができます。
「システム開発」は「要件定義」を明確にすることで、下位の工程が決まります。
「システム開発」以外の社内プロジェクトも「要件定義」を明確にすることで、プロジェクトを円滑にすすめることができます。
「システム開発」の手順・ノウハウを経営に活かすことができます。
6.中小企業経営者が知るべきシステム開発の基礎知識を営業する開発パートナー選びのポイント
「システム開発」の基礎知識は、企業・団体が導入している基幹システムを導入している開発パートナー企業に相談してみましょう。
今回は「ウォーターフォール手法」による「システム開発」を紹介しました。
ITスキルが豊富ではない中小企業経営者の方々には「要件定義」の重要性を認識されたと思います。
「システム」の導入・開発には多額な費用がかかります。
今まで人的資源の作業をコンピューター化することを前提した費用対効果を見極めましょう。
「システム」導入・開発に関しては、企業・団体が導入している基幹システムの開発パートナーに事前相談してみることをお勧めします。
大手電機メーカー、ITベンダー企業、ITベンチャー企業は基幹システムをする部門以外に「システム開発のメリット・デメリット」をサポート・カウンセリングする担当エンジニアをスタンバイさせています。
現行の基幹システムを導入した開発パートナーの営業担当やプロジェクト・マネージャーに相談してみましょう。
まとめ
IT技術経営者ではない中小企業経営者が知るべき「システム開発」の基礎知識を紹介しました。
最上位工程の「要件定義」を固めておかないと下位工程に歪みを生じます。
これは企業経営のなかで「製品開発プロジェクト」「販促プロジェクト」でも「基本方針」を明確にすることと同等です。
企業経営・システム開発も基本方針をしっかり固めてからスタートすることが肝要です。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。