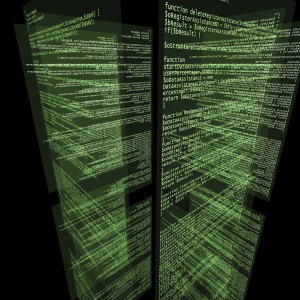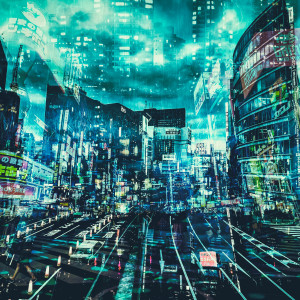ナレッジマネジメントを推進する開発パートナー選びのポイント
「ナレッジマネジメント」という用語を聞いたことがありますでしょうか?最近、ビジネスセミナーやビジネス書で「ナレッジマネジメント」という用語を見受けます。
「ナレッジマネジメント」とは何かを調べてみると、「経営手法のひとつで、組織内にある知識をデータとして集積するだけでなく、知的情報として共有・活用することで組織自体の能力やサービス、製品の性能を高めていくという経営手法」であると説明されていました。
これでは、抽象的でよくわかりません。
これから「ナレッジマネジメント」とは何の理論に準じたものなのか、目的・メリットは何かを紹介していきます。
目次
1.ナレッジマネジメントとは何か?
「ナレッジマネジメント」は英語表記でknowledge managementといいます。
略称はありません。
日本語で紹介すると、企業全体の生産性・優位性を高めるために、個人および組織が持つ企業にとって有益な知識や経験、ノウハウ等を企業内で共有・活用するという経営手法のことです。
ナレッジは、英語でknowledgeと表記します。
意味は「知識」です。
最近のビジネス界では、「個人や組織が持つ知識や経験、ノウハウといった企業にとって有益な知的情報」のことをナレッジと称します。
マネジメントは、英語でmanagementと表記します。
意味は「管理すること」「経営すること」です。
「ナレッジマネジメント」は、有益な知的情報の管理することをいいます。
「ナレッジマネジメント」は、「情報システムによる知識管理」として欧米諸国で広がりました。
しかし、「ナレッジマネジメント」は1990年代前半に日本の経済学者が発表した理論から始まりました。
その理論を「SECI(セキ)モデル」と称します。
「SECI(セキ)モデル」は後の章で紹介します。
日本の商習慣であった終身雇用制度のなかでは、「知識(ナレッジ)」の共有は部門の活性化や部下育成に導入されていました。
従業員が習得した知識を容易に共有できる時代でした。
しかし、企業・団体は古くから継承させていた終身雇用制度・年功序列制度から欧米諸国で導入されている年棒制度や成果主義の働き方に変遷しています。
そのため「知識(ナレッジ)」は個人がもつ大切なスキル・ノウハウになるので、容易に共有できない社会環境になりました。
そのため企業・団体は、「知識(ナレッジ)」をデータとして蓄積する必要性が生じることになりました。
デジタル化推進の風潮が追い風になり、アプリケーションシステムを用いたナレッジマネジメントが注視されるようなりました。
2.ナレッジマネジメントの目的と手法
「ナレッジマネジメント」の目的を紹介します。
ナレッジマネジメントの目的は、「暗黙知」を「形式知」に変え、企業・団体内でIT機器を活用して共有することです。
「暗黙知」「形式知」という聞きなれない用語の紹介をします。
「暗黙知」は、個人(従業員一人ひとり)が有する知識・経験・ノウハウ・勘などの言葉・用語や数値で表記できない知識のことを示します。
「形式知」は、言葉・用語や数値で表記できる知識のことを示します。
明示的知識と呼ばれるがあります。
「暗黙知」を「形式知」に変換し共有できれば、ナレッジマネジメント手法を活用できます。
その活用手法を紹介します。
第1に経営戦略の分析と策定をします。
ナレッジマネジメントを活用することで、組織内・部門内にあり様々な知識を多面的に分析することが可能になります。
その結果は経営戦略策定に活用されます。
第2にベストプラクティス(効率的な方法)の共有をします。
有能な従業員の考え方や行動、ノウハウ等をデータベース化します。
他の従業員が効果的に成果を出すことができます。
第3に顧客(お客先様)知識の共有をします。
お客先様の要望・クレーム・対処方法を組織内・部門内で共有することで、個人差がない共通の対応ができるようになります。
その結果として顧客満足度をアップさせることができます。
第4に専門知識の提供をします。
個人(従業員一人ひとり)が得た専門知識をデータとして蓄積します。
データベース化することで、効率的な運用は可能になります。
ナレッジマネジメントを活用することで、多面的な経営戦略の策定・従業員の業務効率アップ、顧客満足度アップ、従業員のスキルアップなど、企業・団体は効果的な結果を期待することができます。
3.SECIモデル
「SECI(セキ)モデル」を紹介します。
「SECI(セキ)モデル」は、1990年代前半に日本の経済学者が発表した理論です。
ナレッジマネジメントのフレームワークとなる理論モデルのことを示します。
「SECI(セキ)モデル」は、連続していく知識創造のプロセスを表したものです。
連続した知識構造プロセスは下記の通りです。
第1に共同化(Socialization)です。
個人から個人へと「暗黙知」を伝え、同じ経験を行い、「暗黙知」の理解を深めることです。
第2に表出化(Externalization)です。
「暗黙知」を言語・用語や数値化して表記して「形式知」に変えていくことです。
第3に連結化(Combination)です。
「形式知」と「計式知」を組み合わせて、知識体系を作っていきます。
個人の持っていた「暗黙知」は企業・団体の知的財産に遷移します。
第4に内面化(Internalization)です。
連結化で蓄積・構築した体系的した「形式知」を個人へ伝承して「暗黙知」に変換していくことです。
上記4つの要素が繰り返されることで、「暗黙知」は「形式知」に変換されて企業・団体が所有する知的財産になります。
その知的財産から「型式知」が「暗黙知」に変換されることを繰り返します。
上記のように知識創造が連続していくということを「SECI(セキ)モデル」といいます。
Socialization、Externalization、Combination、Internalizationの頭文字4文字から「SEKI(セキ)モデル」と称されるようになりました。
4.ナレッジマネジメントのメリット
「ナレッジマネジメント」のメリットを紹介します。
第1に業務効率化・生産性向上です。
多種多様な知識をデータベース化することができるので、事業所・事業部・部門内の従業員が受けもつ業務が平準化します。
さらに業務の品質の保持ができます。
また、個別の経験・スキル・ノウハウを共有することで、業務中の従業員に難しい課題が生じたときも自分自身で解決できるようになります。
また、業務の平準化により、不要な業務を棚卸して業務の効率化と生産性の向上を図ることができます。
第2に人材育成の効率化です。
新入社員や人事異動で着任した従業員に向けた教育・業務の指導に掛かる工数が軽減化します。
先輩従業員がマンツーマンで指導する場面が少なくなります。
その結果、効率的な人材育成と人材育成費用が削減できるようになります。
第3に顧客マネジメントが向上します。
お客先様の情報の共有することができます。
気難しいお客先様やクレームが多いお客先様の情報とその対処方法を共有できます。
最新のお客先様のニーズを担当部門で共有して、タイムリーな業務をすすめることができます。
5.ナレッジマネジメントのデメリット
「ナレッジマネジメント」のデメリットを紹介します。
第1にシステム導入に初期投資費用と時間が掛かります。
ナレッジマネジメント用のシステム導入には初期投資が必要です。
さらに、従業員がもつ知識・スキル・ノウハウを正確に洗い出して体系化する作業を要します。
作業した情報はデータベース化しますが、本稼働するまでにはデータベースのチューニングを繰り返して実務に向けた整備が必要です。
システム導入は、業務効率化と生産性向上が目的ですが、データの整備をして実用化するまで効果が表れないデメリットがあります。
第2に従業員のシステム利用の定着が課題です。
ナレッジマネジメント・システムを導入後、従業員が当該システムを利活用するか否かは別な課題です。
ナレッジマネジメント・システムを導入してもデータベースを実用化できる状態にして、従業員が当該システムを利活用しないと業務効率化・生産性向上は図れません。
システムが定着するために、システム検討・導入・開発段階で従業員の声を組み込み、全従業員が利用し易い環境を整えることが大切です。
6.ナレッジマネジメントを推進する開発パートナー選びのポイント
「ナレッジマネジメント」機能の採用は、企業・団体が導入している基幹システムの開発パートナーに相談してみることをお勧めします。
大手電機メーカー、ITベンダー企業は基幹システムをする部門以外に「ナレッジマネジメント」を専門にしたサポート担当エンジニアをスタンバイさせています。
現行の基幹システムを導入した開発パートナーの営業担当やプロジェクト・マネージャーに相談してみましょう。
基幹システムを導入した開発パートナー企業は、末端の端末からホストコンピューター・サーバー機の構成を把握しています。
そのため、顧客管理システム・受注管理システム等と連携が必要になる可能性があります。
さらにコールセンター等の事業部があれば、対応履歴をデータ化しているケースがあります。
上記のソースデータを有効に活用するために、「ナレッジマネジメント」システムの導入は、基幹システムを導入した開発パートナー企業に相談しましょう。
まとめ
ナレッジマネジメントの導入目的は、業務効率化・生産性向上です。
しかし、システム導入を急ぎすぎてデータベースが整備されずに運用の開始をすると、落とし穴があります。
従業員がもつ経験・スキル・ノウハウを整理しながらデータベース化すること、定期的な見直しを繰り返してチューニングすることで実用化に向かいます。
同時に、時間を掛けて整備したシステムを全従業員が利活用できる環境を整えることが大切です。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。