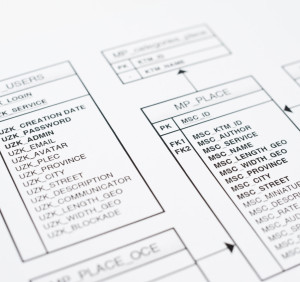アグリテックを推進する開発パートナー選びのポイント
「アグリテック」というIT用語を聞いたことがありますか?農業のことをアグリカルチャーといいます。
「アグリテック」は農業のIT化のことをいいます。
人工知能(AI)・ドローン等の最新IT技術が急速な進化をしています。
いままでは農業分野とIT化は縁遠いものでしたが、最近では「アグリテック」として注視されています。
世界の人口増加による食料不足が、世界規模で懸念されています。
「アグリテック」は食料不足を救済する技術として期待されています。
食・農業にかかわる課題の解決策に限定せずに、地球を持続可能にするテクノロジーとした位置付けされているのです。
目次
1.アグリテックとは何か?
アグリテックとは、アグリカルチャー「農業」とテクノロジー「技術」を組み合わせた造語です。
アグリテックは、農業が抱える課題を、人工知能(AI)・IoT・ビッグデータ・ドローン・ブロックチェーン等の最新IT技術によって解決を目指す技法です。
上記の最新IT技術を活用したアグリテックを用いて、農業の効率化・都市型農業の促進・農業従事者の労働環境改善等の分野での展開が期待されています。
2.アグリテックが注目される背景
アグリテックが食の未来を支援する技法と注視されるようになった背景は、農業における深刻な課題が明確化されたことです。
世界的に懸念されているのが食料不足です。
先進国の日本も例外ではありません。
これからアグリテックが注目される背景を紹介します。
第1に世界における農業の課題です。
世界的に懸念されていることが深刻な食料不足です。
農産物輸出国は低価格で取引をするため、農業従事者の賃金が搾取されてしまう課題があります。
月給が円換算で千円の輸出国があるのです。
その課題の解決策として、アグリテックが注視されています。
第2に深刻な食料不足の危機を救うことです。
少ないコストで大きな供給を提供する仕組みのアグリテックが注目されています。
2022年の世界の人口は約78憶人です。
2050年には100憶人まで増加すると予測されています。
人口増は深刻な食料不足が危惧されています。
食料不足は、国際的な対立を生みかねない問題として懸念されています。
しかし、アグリテックの進化により安心安全な食料供給が期待されています。
第3に農業従事者の賃金搾取をなくすことです。
先進国が農作物を低価格で輸入するために、新興国の農業従事者は低賃金で重労働をする実態があります。
特に日本の国産農作物は、新興国からの技能実習生として来日した若者が担っているのです。
技能実習生は、日本人の労働者と比較して、6割程度の人件費で働いています。
しかし、アグリテックの進化により、最小限の労働力に移行し、農業従事者の同一労働同一賃金に是正することが期待されています。
3.日本国内の農業課題を救うアグリテック
日本国内の農業課題を救うアグリテックを紹介します。
第1にアグリテックによる生産効率化で食料自給率を上げることです。
農林水産省は、「2030年までに積極的にアグリテックを日本農業界に導入することによって、農業や生産の効率化を目指す」と発表しました。
日本国内の食料自給率は、1965年は73%ありました。
しかし、2019年には約半数の38%まで低下しています。
先進国で食料自給率が38%の国は日本しかありません。
もし、海外からの食料輸入に頼れない状況になってしまった場合、日本は深刻な食料不足に陥るか?食料品のインフレ化がすすむといわれています。
上記の最悪なシナリオを救済する技法として期待される「アグリテック」の迅速な開発と導入が進められているのです。
第2に重労働である農作業の省略化によって農業従事者の負担削減をすることです。
アグリテックの導入で、作業の簡略化と効率化を図ることで、高齢者を含む農業従事者の負担を軽減できるといわれています。
2019年の統計では、日本の農業従事者の平均年齢は67.0歳です。
さらに、65歳以上の高齢者の農業従事者は、業界の人口の70%以上を占めています。
顕著な農業従事者の高齢化です。
作業の機械化と最新IT化が進んでいるとようですが、高齢者にとって体力的に厳しい作業が多い業界です。
アグリテックを導入し、農業従事者の負担を軽減することで「きつい」「汚い」「危険」の「3K」と呼ばれる負のイメージが改善されと期待されています。
4.アグリテックの4つのテクノロジー
アグリテックの4つのテクノロジーを紹介します。
第1に人工知能(AI)とビッグデータの分析です。
農業従事者の経験・ノウハウに関わらずに、人工知能(AI)を用いたドローン・センサー等で収集したビッグデータを分析して、高品質の耕作物を栽培・収穫できる最新IT技術です。
ベテランの感や経験ですすめている農業の技術を情報として可視化して提供することができます。
たとえば、農作物の害虫被害・疫病の可能性と対処法・収穫時期の見極め等、収穫ロスを生じさせない成功例をデータ上で確認することが可能になっています。
第2にIoT(Internet of Things)です。
IoTはモノのインターネットという意味をもちます。
センサー機器をインターネットに接続することで、遠隔地にあるモノの状態を24時間365日管理できる技法です。
いままでは、人的資源が担っていた在庫管理を収穫した耕作物・機材・機械にセンサーを実装することで、農場工程全般をパソコンで可視化することができます。
第3にブロックチェーンです。
ブロックチェーン(仮想分散化台帳履歴管理)の技術は、安心・安全で透明なサプライチェーン構築のために有効です。
モノが国家間を移動しあう時代です。
複雑なサプライチェーン(供給連鎖)の仕掛けが増大したことにより、トレーサビリティー(追跡可能性・追跡履歴)が不透明に至ることがあり得ます。
そこで、ブロックチェーン技術を活用することで、サプライチェーン(供給連鎖)をより単純でトレーサビリティーの高い仕組みに改新できるのです。
第4にドローンの活用です。
いままでは、人的資源で作業をしていた種まき・農薬散布等をドローンの導入で、効率よく機械化へ移行できます。
くわえて、ドローンの操縦スキルがなくとも人工知能(AI)機能が耕作地全体をフォローするようになります。
5.「食」「環境」「サプライチェーン」を持続可能にするアグリテック
「食」「環境」「サプライチェーン」を持続可能にするアグリテックを紹介します。
第1に「食」です。
アグリテックの進化により、安定した食料供給を維持することができます。
2050年までに、世界の人口が100億人を超えると予想されるなかで、少ないモノで多くのモノを生み出すことができることが理想とされます。
農業にかかるコストを最小限抑制して、耕作物の生産と収穫量をアップさせる技術であるアグリテックに期待されています。
第2に「環境」です。
人工知能(AI)とビッグデータ分析の技術を活用することで、大気の状況・土壌状況を分析し、効率的に資源を活用することができます。
全世界の農業によるCO2排出量は全体の1/4を占めています。
食料供給量を満たすことは重要です。
しかし、CO2排出量を放置することは許されません。
第3にサプライチェーン(供給連鎖)です。
前章で紹介しましたが、サプライチェーンが不透明で複雑であると、輸入する耕作物の背景に農業従事者からの違法搾取・農業従事者の低賃金労働などの問題点が多くあり得ます。
アグリテック導入で安心・安全なサプライチェーンを可能にして、国連が掲げている持続可能性の貢献が可能になります。
6.アグリテックを推進する開発パートナー選びのポイント
アグリテックは、人工知能(AI)機能を搭載したドローンや農業耕作機器のIT化が推進されていきます。
近年では、農作物の収穫ロボットの導入が始まっています。
人的資源による作業から、最新IT機器の導入により自動化・効率化が進んでいます。
アグリテックの導入により、人材不足問題の解決・危険な作業を削減することができます。
開発パートナー企業を選択するときは、農業耕作機器のIT化・人工知能(AI)機能を搭載したドローンを扱う企業に絞られていきます。
農業法人であれば、基幹情報システムをサポートする開発パートナーと連携したアグリテック機器を検討して、できることから自動化していきましょう。
また、新規にアグリテックを検討するときは、アグリテックの仕組みを導入した実績を多く持つ、大手電機メーカーや大手ITベンダー企業を選択することをお勧めします。
まとめ
世界の人口増加が止まらない環境下で、将来起こり得る深刻な食料不足を救える可能性を秘めたアグリテック技法が期待されています。
アグリテック導入の背景は、現状のままの農業と消費を続けていると、2050年には深刻な食糧不足に至るようです。
特に我が国は、食料自給率が約38%と極めて低い状況です。
輸入に食料供給を頼っている日本も例外ではありません。
今後、アグリテック技法の進化が期待されています。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。