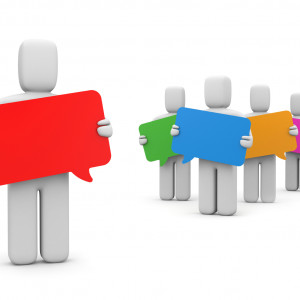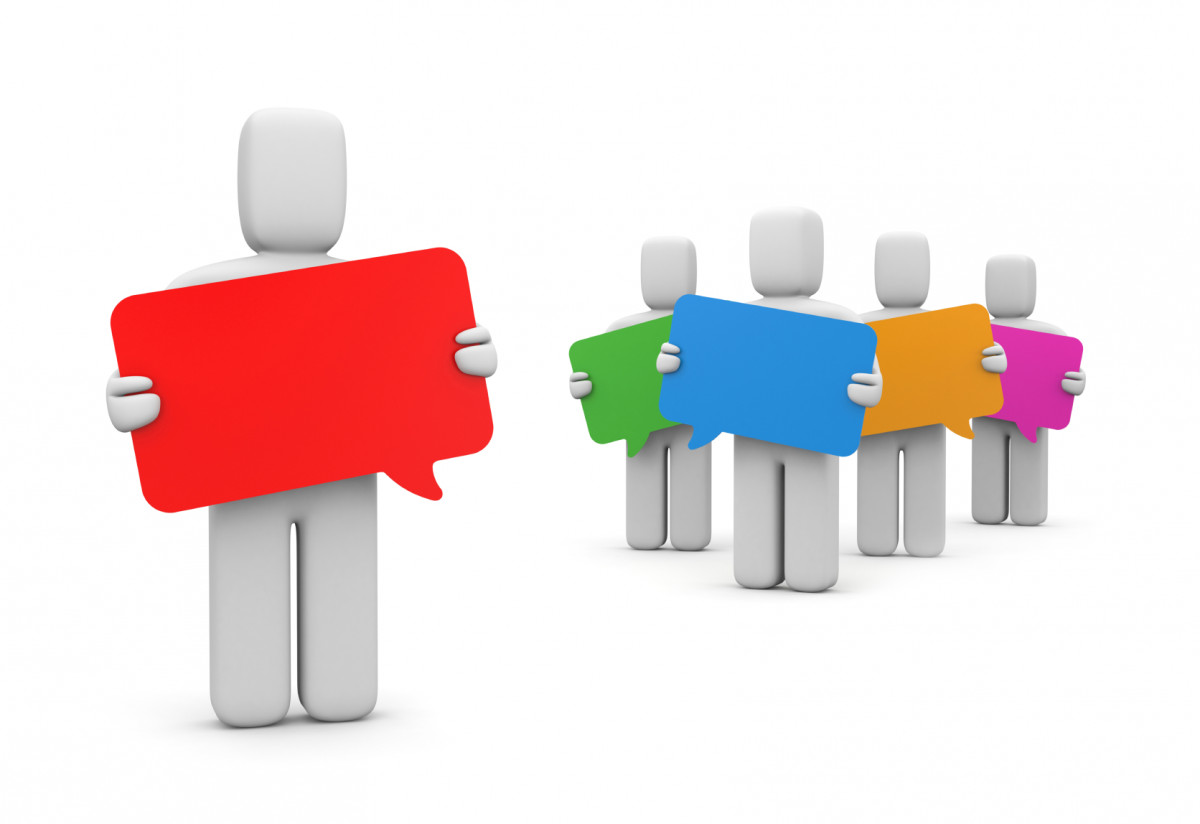
インボイス制度施行を支援する開発パートナー選びのポイント
「インボイス制度」という用語をご存知でしょうか? 英語表記の「Invoice」とは異なります。
「Invoice」は貿易で使用される取引内容を記載した「送り状」です。
これから紹介する「インボイス制度」は、軽減税率制度により複数の税率が制定されたとき、仕入れ税額控除に適格請求書(インボイス)の保存が要件となる制度をいいます。
軽減税率制度とは、標準税率より低い税率を適用すること、又は適用される税率のことです。
2019年10月1日に導入された消費税の軽減税率制度のことを示すことが多くあります。
2019年10月1日の導入時の標準税率は10%ですが、食料品は2%軽減されています。
「インボイス制度」は売り手・買い手ともに適用される制度です。
売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、「適格請求書(インボイス)」の交付が非必要になります。
買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。
「インボイス制度」は、「適格請求書保存方式」のことです。
決められた記載要件を満たした請求書等が「適格請求書(インボイス)」になります。
確定申告・消費税申告の際に「適格請求書(インボイス)」発行または保存したもの基づき、消費税の仕入額控除を受けることできます。
控除を受けるときに「適格請求書(インボイス)」が必要になるのです。
この「インボイス制度」が2023年10月1日から導入される予定です。
「インボイス制度」が導入されることにより、売上規模の小さな個人事業主、フリーランスの方に大きな影響がある可能性があると話題にあがっています。
「インボイス制度」の適用を受けるために「適格請求書発行事業者」への登録が必要です。
「適格請求書発行事業者」の登録申請は、2021年10月1日から受け付けが開始されています。
これから「インボイス制度」の仕組みを紹介していきます。
目次
1.インボイス制度とは何か?
2023年10月に施行する「インボイス制度」は、登録を受けた課税業者が法的効力のある「適格請求書(インボイス)」を発行できるとういう新しい制度です、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
「適格請求書(インボイス)」は、取引実績がある事業者が発行した請求書・納品書・領収書へ項目を追記することになります。
「インボイス制度」は、以下6項目が記載されることが義務付けられます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である理由)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称です。
2019年9月までの消費税率は一律でしたが、翌月から軽減税率制度が導入されました。
複数の適用税率があるので、消費税申告納税額の不備や不正を抑止する対策といわれています。
「インボイス制度」導入後は、「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することが仕入税額控除の適用要件になります。
「適格請求書(インボイス)」を発行するためには、税務署へ登録申請をする必要があります。
登録申請の対象は「課税事業者」です。
つまり、免税事業者は「適格請求書(インボイス)」を発行することができません。
なお、税務署への登録申請は2021年10月1日に始まっています。
2.「課税事業者」「免税事業者」
消費税を納税する「課税事業者」と納税が免除させる「免税事業者」があります。
「インボイス制度」の理解には、「消費税」の仕組みを認識することです。
消費税は今から33年前の1989年4月1日に導入され、当時の税率は3%でした。
当時は年間売上高が3,000万円未満は免税業者、それ以外は課税業者とされていました。
その後、課税対象要件が変遷して、消費税を納税する「課税事業者」と一定の要件を満たすと消費税納税が免除される「免税事業者」に2分されています。
「課税事業者」は、前々年の課税売上(消費税込みの売上高)合計が1,000万円超の事業者が対象になります。
「免税事業者」は、前々年の課税売上(消費税込みの売上高)合計が1,000万円以下の事業者が対象になります。
また、事業開始から2年未満の場合は「免税事業者」になり、消費税の納税が免除されます。
売上規模の小さな個人事業主・フリーランスの方は、「免税事業者」に該当するケースが多いようです。
確定申告・青色申告時の納税に影響はないようです。
「課税事業者」は、消費税の納税義務があります。
納税しないと脱税になります。
事業者が仕入時に支払いをした商品の消費税は納税分から差し引くことができます。
この差し引きを「仕入税額控除」といいます。
「課税事業者」が重複して消費税を納めることを防ぐための軽減制度です。
「課税事業者」が納税する消費税の金額=「税込販売価格の消費税分」―「仕入で支払いした消費税」の計算式になります。
たとえば、税込販売価格の消費税が10,000円、仕入で支払いした消費税が3,000円というケースでは、10,000円−3,000円=7,000円を納税します。
3.インボイス制度開始でフリーランスはどうなるか
「インボイス制度」開始でフリーランスの消費税納税はどうなるのでしょうか? フリーランスの方々は「免税事業者」ですので「適格請求書(インボイス)」が発行できません。
そのため「課税事業者」がフリーランスと取引すると、仕入時の消費税免税控除の証明書が入手できません。
「課税事業者」は「適格請求書(インボイス)」がないため、フリーランスから仕入れを商品の商品税を負担して納税することになります。
現在、フリーランスは「免税事業者」として営業活動をしていますが、「適格請求書(インボイス)」発行ができないため、フリーランスの方々の売上高に影響があります。
「課税事業者」は免税事業者の証明がないフリーランスと取引をするとき、仕入額控除が適用になりません。
そのため、消費税分を値引きした取引形態にせざるを得ません。
結果的にフリーランスは消費税額分の売上が減少することになります。
前章で紹介しましたが、課税売上合計が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」ですが、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば「課税事業者」に変更できます。
「適格請求書発行事業者」の登録申請をするときに、上記届出書を添付すれば手続きが可能になります。
最終的に「課税事業者」は消費税の納税義務があります。
年間売上高から消費税分の納税をするので、利益減になります。
4.登録申請は2021年10月に開始されています
税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請する手続きは、2021年10月1日に開始されています。
「インボイス制度」が施行する時期は約22ヶ月先の2023年10月1日です。
まだ、22ヶ月先といっても、あなた自身の事業の展開と売上目標を勘案して、年間の売上高が1,000万円を超過するときは「適格請求書(インボイス)」の取り扱いをする義務があります。
法制化されていますので、売上高が1,000万円を超えて「適格請求書発行事業者」に登録していないと処罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)されますので、気を引き締めてください。
また、「インボイス制度」導入にあたり経過措置期間があります。
免税事業者が発行する請求書等が「インボイス制度」導入後、直ちに仕入税額控除の対象から外れません。
2023年10月1日〜2026年9月末日までは仕入額相当額の80%、2026年10月1日〜2029年9月末日までは仕入額相当額の50%が認められる「みなし仕入率」があります。
税務署が開く講習会・地元の商工会議所が開く講習会への出席をお勧めします。
また、青色申告会に加入している事業主・フリーランスの方は、担当者に相談してみましょう。
5.インボイス制度施行を支援する開発パートナー選びのポイント
「インボイス制度」対応は、企業・団体が導入している基幹システム(特に会計・経理・財務システム)の開発パートナーは制度施行の対応をすすめています。
また、個人事業主・フリーランスの方々が導入している会計アプリケーションも「インボイス制度」についてサポート体制を整備しています。
ご自身が導入して会計アプリケーションの製造元もHPを閲覧すると2029年9月までの「措置期間」「みなし仕入率」にタイムチャートが掲載されています。
また、年間保守契約を締結していれば、通知がありますので安心しましょう。
また、会計アプリケーションの製造元である大手電機メーカー、ITベンダー企業、ITベンチャー企業は基幹システムをする部門とは別に「インボイス制度対策」支援サポート部門があります。
現行の基幹システムを導入した開発パートナーの営業担当やプロマネに相談してみましょう。
まとめ
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式の「インボイス制度」が施行します。
「インボイス制度」は「適格請求書発行事業者」に申請・登録しないと取り扱いができません。
国税庁の「インボイス制度」に関する説明書は、『霞ヶ関語』で記述されているのでよくわかりません。
前章で紹介しましたが、説明会・講習会に参加して、事前準備をして施行に備えましょう。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。