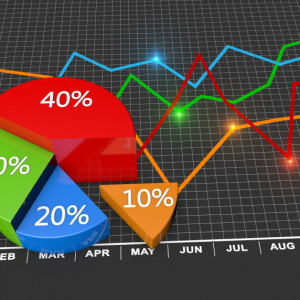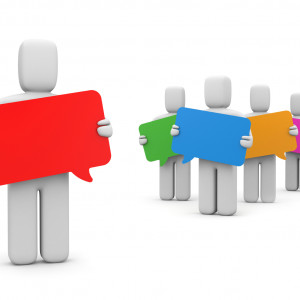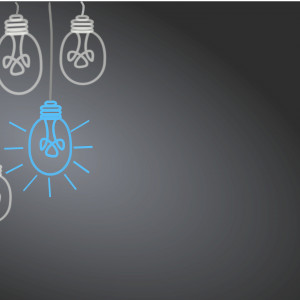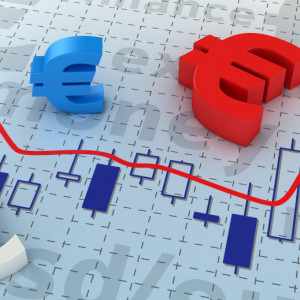ウェビナーを推進する開発パートナー選びのポイント
「ウェビナー」という用語を聞いたことがありますでしょうか?「ウェビナー」は「ウェブ(Web)」と「セミナー」を組み合わせた造語です。
インターネット経由で実施されるオンラインセミナーのことを示します。
また、セミナーを実施するためのツール(Zoom等)を含むことがあります。
2019年末に発生した新型コロナウイルス感染症はパンデミックを引き起こしました。
人々の行動制限や外出規制が行われるなかで、在宅勤務・テレワーク勤務とオンライン会議、Web上のセミナーが注目されました。
セミナーは、講義・講演会・研修会のことです。
従来のセミナーは会館・ホール・会議室を使って、聴講者が出向いて参加していました。
「ウェビナー」は聴講者が出向くことなくインターネット経由で講義・講演・研修会に参加できる機能です。
インターネット環境があれば、どこからでも参加することができます。
これから「ウェビナー」の概要とメリット・デメリットを紹介していきます。
目次
1.ウェビナーとは何か?
「ウェビナー」は、英語表記でWebinarといい、Web(ウェブ)とSeminar(セミナー)を組み合わせた造語です。
ウェブセミナー・オンラインセミナーのことです。
主にインターネット経由で実施されるセミナー・研修会・講習会を指します。
また、「ウェビナー」に参加するためのツールを含みます。
「ウェビナー」への参加者・聴講者は、インターネット環境があれば、パソコン・タブレット端末・スマートフォン等のモバイル端末を使用して、どこからでも参加できます。
2.ウェビナーの配信方法
「ウェビナー」の配信方法を紹介します。
第1にリアルタイム配信です。
リアルタイム配信は、決められた日時にセミナー・講習会を配信する方法で、ライブ配信ともいいます。
コロナ禍で歌手のコンサート・アーティストの演奏会はライブ配信されることが多くなりました。
第2に動画配信です。
動画配信は、主催者が事前に録画した動画を、セミナー・研修会の動画として配信する方式です。
リアルタイムで配信(またはライブ配信)するケースと異なり、配信時間に定めがありません。
参加者・聴講者はいつでもどこからでも「ウェビナー」を視聴するできることできます。
3.ウェビナーのメリット
「ウェビナー」のメリットを紹介します。
第1にセミナー・講習会の開催コストが削減できます。
参加者・聴講者の獲得を目的としたセミナー・講習会を運営するときは、会館・ホール・会議室を借りて開催します。
会場を借りるために会場費用が発生します。
また、会場に配置する運営スタッフを雇う必要があります。
「ウェビナー」の開催では、会場費・運営スタッフ費用が不要になり、開催コストが削減できます。
さらに参加者・聴講者は会場に出向く往復の移動時間と交通費が不要になります。
第2にいつでもどこでも視聴することが可能です。
参加者・聴講者はインターネット環境があれば、パソコン・タブレット端末・スマートフォンを使用して、どこからでも視聴することができます。
また、動画配信の「ウェビナー」は、都合の良い日時に視聴することができます。
第3に会場・人数に制約がなく新規参加者開拓の機会を拡大できます。
「ウェビナー」は会場・人数に制約がなくなります。
また、敷居が高いとされるセミナーや参加者層の年代が合わないセミナー・研修会に参加することができます。
いままでの会場参加型のセミナーでは、参加を見送りしたテーマのセミナーに参加することができます。
4.ウェビナーのデメリット
「ウェビナー」のデメリットを紹介します。
第1に通信環境によって品質に差が出ることです。
利用者の皆さんが用意されている通信インフラ機器・配信された画像を見るパソコン・タブレット端末・スマートフォンのスペックによって音声・画質に差がでる可能性があります。
特に無線のモバイルルーター機器を利用しているケースでは、映像が一時的に停止することがあります。
この事象は開催側・運営側で防ごうとしても、利用者皆さんの利用環境が一人ひとり異なるので、防ぎきれないというのが現状です。
動画配信は再生できますが、リアルタイム配信は再生できません。
通信インフラ環境に不安があるときは、録画機能を活用できるようにしておきましょう。
配信が終っても事後確認することができます。
第2にセミナー参加者の熱量が測りづらいことです。
会場・ホールで行われるセミナーと異なり「ウェビナー」は、参加者・聴講者の表情・雰囲気が確認できないため、熱量を感知できません。
開催側・運営側は、「ウェビナー」上のアンケート等で確認しましょう。
5.ウェビナーツール選定のポイント
「ウェビナー」ツール選定のポイントを紹介します。
第1に料金プランです。
「ウェビナー」ツールの料金プランは「月額固定制」「従量課金制」があります。
「月額固定制」月額利用料金が固定性なので「ウェビナー」の開催回数が多いケースはおすすめです。
また、「従量課金制」は使用分だけの料金になります。
「ウェビナー」の開催回数が少ないケース・不定期開催セミナーのケースにおすすめです。
第2に必要な機能を確認しましょう。
「ウェビナー」セミナーがリアルタイム配信のケースでは、チャット機能を使用するときがあります。
参加者の質問や疑問応対形式の「ウェビナー」があります。
そのときは、チャット機能を使用して質問・疑問を問い合わせできます。
第3にサポート体制です。
「ウェビナー」ツールを提供するベンダー企業のサポート体制が整備させているか確認しましょう。
最近のアプリケーションソフトウエアはサポート体制が充実しているツールを選択するようになっています。
事前にどのようなサポート体制が整備されているか確認しましょう。
6.ウェビナーツール
「ウェビナー」ツールを紹介します。
第1に「Zoom Webinar」です。
アメリカ合衆国のZoomビデオコミュニケーションズ社製のクラウドコンピューティングを使用したWeb会議サービスです。
「Zoom(ズーム)」は、世界で75万社の企業が導入しています。
特徴は
- 参加100名まで無料プランで対応可能なことです。
- ホスト以外はアカウントの作成不要で参加者の招待が簡単にできます。
- Web会議の内容の録画や録音をワンクリックで対応可能であることです。
第2に「コクリポ」です。
東京都渋谷区に本社を構える株式会社コクリポ社製の「ウェビナー」専用のアプリケーションソフトウエアです。
「コクリポ」は、時間換算3,000円で炉用できる月額制「ウェビナー」ツールです。
利用者のインストールが不要で最大300名様へのライブ配信が可能です。
特徴は
- 回線が安定し自動再接続機能もあるため、ストレスなく続行できることです。
- 視聴している時間を記録できるため、参加者各個人に合わせたフォローができることです。
- 利用者のインストールが不要で参加しやすいことです。
第3に「Live On」です。
東京都千代田区に本社を構えるジャパンメディアシステム株式会社製の安価で品質が優れたWeb会議システムサービスです。
月額3,000円で使い放題のメリットがあります。
数多くWeb会議を実施する企業・団体はコスト削減が期待できます。
特徴は
- 完全自社開発の製品で高品質の音質と画質を実現しています。
- 日本語・英語・中国語にも対応しています。
- 直感的なインターフェースで簡単操作が可能なことです。
第4に「V-CUBEセミナー」です。
東京都港区に本社を構える株式会社ブイキューブ社製のウェブセミナーのライブ配信・オンデマンドコンテンツの配信を行うクラウド型配信サービスです。
全世界のパソコン・タブレット端末に対してセミナーを配信することが可能です。
特徴は
- チャット・アンケートによる双方向コミュニケーションができます。
- 24時間365日サポート対応をしています。
- 利用者に合わせた運用体制の構築を支援します。
第5に「ネクプロ」です。
東京都中央区に本社を構える株式会社ネクプロ社製の「ウェビナー」を通じでのマーケティング活動全般を行う機能を提供するサービスです。
顧客層の拡大を課題にしている企業・団体におすすめのツールです。
特徴は
- 参加・視聴したお客先様管理を極め細かく管理できます。
- セミナー運営に関わる繁雑な業務を一元管理します。
- 過去の動画を扱い、資料ダウンロードとアンケートを組み合わせたビジネスモデルを展開できます。
7.ウェビナーを推進する開発パートナー選びのポイント
「ウェビナー」は、企業・団体が導入している基幹システムとの連携は必要ありません。
但し「ウェビナー」でセミナーに参加・視聴した利用者様情報を顧客管理システムに登録すること、チャット機能を使用したメッセージを蓄積して機械学習(人工知能(AI)で利用します。)するソースデータとして活用することが考えられます。
「ウェビナー」「Webセミナー」ツール導入については、企業・団体が導入している基幹システムの開発パートナーに相談してみることをお勧めします。
大手電機メーカー、ITベンダー企業は基幹システムをする部門とは別に「ウェビナー」「Webセミナー」ツールの支援サポート部門があります。
現行の基幹システムを導入した開発パートナーの営業担当やプロジェクト・マネージャーに相談してみましょう。
まとめ
「ウェビナー」の導入によって、多人数を対象としたセミナー開催が可能になります。
お客先様が求めている情報提供をライブ配信・動画配信することができます、さらにセミナーに参加・聴講したお客先様方法を取得できるメリットがあります。
販路を拡大する機会が待っています。
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば
システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。
以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。